これってパワハラ?上司 部下 同僚別 実例をもとに徹底解説
「これってパワハラ?」「どこからがアウトなの?」
職場で上司や同僚から厳しい指導を受けたり、理不尽な要求をされたりしたとき、多くの人がそう悩みます。一方で、「最近の若者は打たれ弱い」という声もあり、指導との線引きが曖昧になっているのも事実です。
パワハラの判断基準は、個人の感情だけではありません。法律で明確な定義が定められており、「上司から部下へ」だけでなく、「部下から上司へ(逆パワハラ)」や「同僚間」のハラスメントもパワハラに認定されます。
この記事では、厚生労働省が定めるパワハラの定義を基に、「どこからがパワハラなのか?」という疑問に答えます。さらに、上司・部下・同僚という関係性別の具体的なパワハラ事例を、実際に報道された事件やニュースと関連付けながら、詳しく解説します。
そもそも「パワハラ」とは?法律による3つの定義
まず、パワハラの定義について確認しましょう。感覚的に「嫌がらせ」と感じるものが全てパワハラになるわけではありません。
労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)では、職場のパワーハラスメントを以下の3つの要素をすべて満たすものと定義しています。
- ① 優越的な関係を背景とした言動であること
職務上の地位(上司など)だけでなく、専門知識、経験、人間関係など、様々な「優位性」が背景になり得ます。部下や同僚が集団で行う嫌がらせも、数的優位からこれに該当します。 - ② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであること
社会通念に照らし、その言動が明らかに業務上の必要性がない、またはそのやり方が不適切である場合を指します。業務上の必要な指導や注意は、パワハラにはあたりません。 - ③ 労働者の就業環境が害されるものであること
その言動によって、労働者が身体的または精神的に苦痛を感じ、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、仕事をする上で看過できない程度の支障が生じることを指します。
この3つが揃って初めて、法律上の「パワハラ」と認定されます。それでは、この定義を具体的な事例に当てはめて見ていきましょう。
【関係性別】パワハラの6類型と具体的なニュース・事件事例
厚生労働省は、パワハラの典型的な言動を6つの類型に分類しています。ここでは、その6類型を「上司から部下へ」「部下から上司へ」「同僚間」の3つの関係性に分けて、実際の事件にも触れながら解説します。
ケース1:上司から部下へのパワハラ事例
最も一般的で認識されやすいのが、上司から部下へのパワハラです。職務上の地位という明確な優越性を背景に行われます。
① 身体的な攻撃
<具体例>
- 殴る、蹴る、物を投げつける
- 胸ぐらをつかむ、髪を引っ張る
<関連ニュース・事件>
2017年、大手ゼネコンの現場監督が部下の頭を殴るなどの暴行を加え、部下が精神疾患を発症したとして労災認定されました。この事件では、日常的な暴力が「指導」の名の下に行われていた実態が明らかになりました。言うまでもなく、暴力は指導の範囲を逸脱しており、傷害罪に問われる可能性もある悪質な行為です。
② 精神的な攻撃
<具体例>
- 「給料泥棒」「小学生以下の仕事しかできない」など、人格を否定する暴言を吐く
- 他の社員の前で、長時間にわたり執拗に叱責する
- 脅迫や名誉毀損にあたる発言をする
<関連ニュース・事件>
近年、多くの企業で問題となっているのが、この精神的な攻撃です。某有名アパレル企業では、上司が部下に対し「お前の存在が目障りだ」といった暴言を繰り返し、部下がうつ病を発症。裁判所はこれをパワハラと認定し、会社側に損害賠償を命じました。人前での叱責が「公開処刑」のように行われるケースは、被害者の尊厳を著しく傷つける典型的な精神攻撃です。
③ 人間関係からの切り離し
<具体例>
- 一人だけ別室に席を移させ、誰ともコミュニケーションを取らせない
- 会議や重要な連絡事項から意図的に外す
- 歓送迎会などの社内イベントに一人だけ呼ばない
<関連ニュース・事件>
大手電機メーカーで、ある社員が内部通報を行ったことをきっかけに、上司から別室への隔離を命じられ、一切の業務を与えられないという事件がありました。これは「追い出し部屋」とも呼ばれ、自主退職に追い込むための悪質なパワハラとして社会問題化しました。仕事に必要な情報を与えず孤立させる行為は、業務の遂行を妨害するだけでなく、被害者に深刻な孤独感と疎外感を与えます。
④ 過大な要求
<具体例>
- 新入社員に、到底達成不可能な営業ノルマを課す
- 業務とは全く関係のない、私的な用事(家の掃除、子どもの送迎など)を強制する
- 連日の徹夜や休日出勤をしなければ終わらない量の仕事を押し付ける
<関連ニュース・事件>
2015年に広告代理店で起きた過労自殺事件は、この過大な要求が背景にあるとされています。月100時間を超える残業に加え、上司からの「髪がボサボサ」「目が充血したまま出社するな」といった精神的プレッシャーも重なっていたと報道されています。本人の能力や経験を無視した業務命令は、心身を破壊する危険なパワハラです。
⑤ 過小な要求
<具体例>
- 専門職として採用した社員に、一日中シュレッダーがけやコピー取りしかさせない
- 営業職の社員から仕事を取り上げ、何の指示も与えず放置する
<関連ニュース・事件>
これは③の「人間関係からの切り離し」と関連して行われることも多い手口です。退職させたい社員に対し、意図的にキャリアや能力に見合わない単純作業のみを延々と命じるケースがこれにあたります。本人の成長機会を奪い、自尊心を傷つける行為であり、目的が退職勧奨であれば違法と判断される可能性が高まります。
⑥ 個の侵害
<具体例>
- 交際相手や配偶者について、執拗に聞いたり、悪口を言ったりする
- 年次有給休暇の取得理由を根掘り葉掘り聞き、認めない
- SNSを監視し、投稿内容について職場で言及する
- 思想や信条、宗教、性的指向(SOGI)などを本人の許可なく他の社員に暴露する(アウティング)
<関連ニュース・事件>
2020年にパワハラ防止法が改正された際、この「個の侵害」の中に、SOGIハラやアウティングが含まれることが明記されました。過去には、大学院でアウティングをきっかけに学生が精神的苦痛を受け、転落死するという痛ましい事件も起きています。プライベートへの過度な干渉は、個人の尊厳を侵害する許されない行為です。
ケース2:部下から上司へのパワハラ(逆パワハラ)事例
近年増加傾向にあるのが、部下から上司への「逆パワハラ」です。年上の部下や、特定のスキルを持つ部下、あるいは部下たちが集団になることで、上司より優位な立場に立ち、ハラスメントが行われます。
<具体例>
- 上司の指示を「そんなやり方、古いですよ」と集団で無視し、業務を妨害する。
- ITスキルが低い上司を「デジタル音痴」などと公然と馬鹿にし、必要な情報を共有しない。
- 「それってパワハラですよ」という言葉を濫用し、正当な業務指示に従わない。
- SNSや社内チャットで上司の誹謗中傷を書き込む。
<関連ニュース・事件>
ある地方自治体で、複数の部下が新任の女性課長に対し、集団で挨拶を無視したり、指示をボイコットしたりする嫌がらせを繰り返した事例が報道されました。このケースでは、第三者委員会が「集団による逆パワハラ」と認定しています。「集団の力」という優越性を背景に、特定の個人を孤立させ、精神的に追い詰める悪質な行為です。
ケース3:同僚間のパワハラ事例
役職上の上下関係がない同僚間でも、パワハラは起こり得ます。社歴、年齢、スキル、性格、あるいは単なる「無視」といった行為でも、継続的・集団的に行われれば、優越的な関係性が生まれ、パワハラと認定されます。
<具体例>
- 特定の同僚のミスを、必要以上に大声で指摘したり、部署内に言いふらしたりする。
- 自分より社歴の浅い同僚に対し、雑用をすべて押し付ける。
- ランチや飲み会に、意図的に一人だけ誘わない。
- 業務上必要な情報をわざと共有せず、孤立させる。
<関連ニュース・事件>
大手保険会社のコールセンターで、複数の同僚が特定の1人に対し、「臭い」などと書いたメモをデスクに貼る、陰口を言うなどのいじめを繰り返した事件がありました。裁判所は、これを同僚間のパワハラ(いじめ)と認定し、加害者と会社の双方に賠償を命じました。同僚という対等なはずの関係でも、集団による無視や陰口は、被害者を精神的に追い詰める十分な「暴力」となり得ます。
まとめ:パワハラは「関係性」と「業務の適正範囲」が鍵
ここまで見てきたように、パワハラは上司から部下への一方的なものだけではありません。
- 上司から部下へ:地位や権力を利用した、最も典型的なパワハラ
- 部下から上司へ:集団の力や専門知識を背景とした、逆パワハラ
- 同僚間:社歴や人間関係の優位性を利用した、いじめ型のパワハラ
どのような関係性であっても、「優越的な関係」を背景に、「業務の適正な範囲を超えて」、相手に「精神的・身体的苦痛」を与えれば、それはパワハラです。
もしあなたが「これってパワハラかも?」と感じたら、一人で抱え込まないでください。
- 記録する:いつ、どこで、誰に、何を言われた・されたかを具体的にメモや録音で記録しましょう。
- 相談する:社内のハラスメント相談窓口や、信頼できる上司・同僚に相談しましょう。
- 外部機関を利用する:社内での解決が難しい場合は、労働局の「総合労働相談コーナー」や、弁護士などの専門家に相談する選択肢もあります。
この記事が、職場のハラスメントに悩むすべての方にとって、現状を整理し、次の一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。

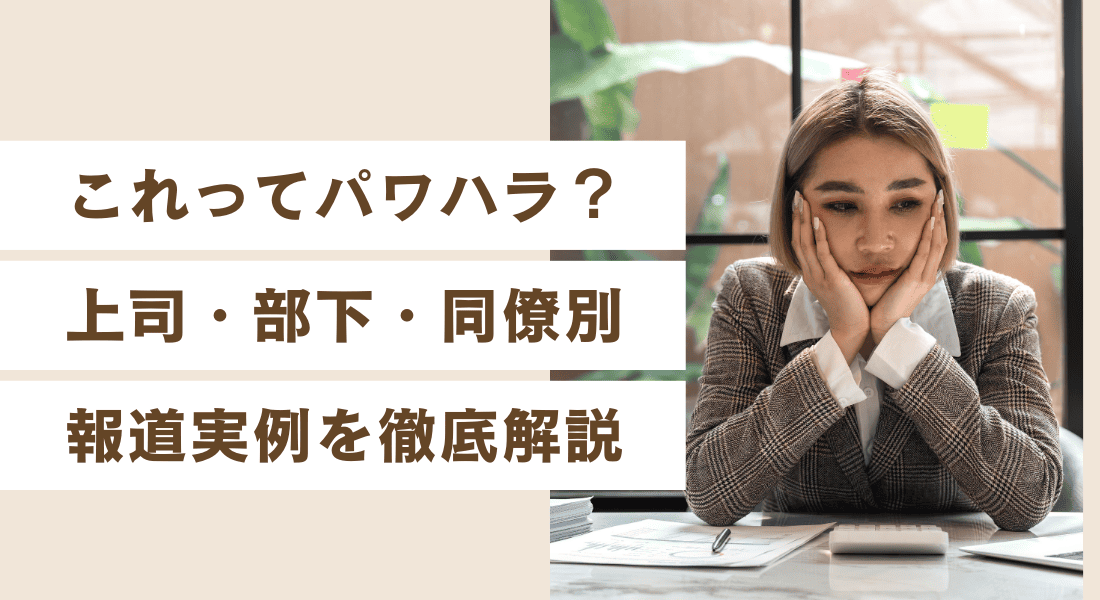

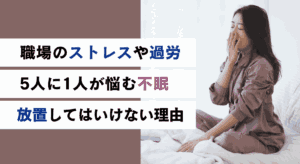
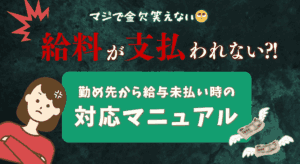





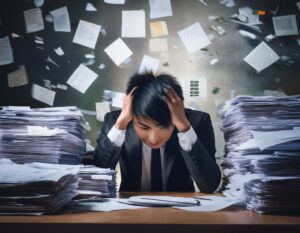
コメント