自己都合退職の失業手当はいつから?年収300万円のリアル収支|給付制限1ヶ月短縮後の完全ガイド
「キャリアアップのために転職したい」「新しいことに挑戦したい」
自らの意思で退職を決意する「自己都合退職」。希望に満ちた一歩である一方、一番の不安は「お金」のことではないでしょうか。
特に、2025年4月から失業手当のルールが大きく変わりました。この変更を知らないと、あなたの退職後の計画が大きく狂ってしまうかもしれません。
この記事では、年収300万円(月収25万円)、勤続1年(雇用保険の加入期間は通算5年)という具体的なモデルケースを使い、最新の制度に基づいて、あなたがもらえるお金、支払うお金、そしてリアルな生活収支を徹底的にシミュレーションします。
「退職してから、お金がもらえるまでどのくらいかかるの?」
「結局、毎月いくら手元に残るの?」
そんな疑問をすべて解消し、安心して次のステップに進むための「お金の羅針盤」となる記事です。ぜひ最後までご覧ください。
【最重要】2025年4月〜の変更点!失業手当の給付制限が原則「1ヶ月」に
本題に入る前に、今回のシミュレーションの前提となる非常に重要な法改正について解説します。
これまで自己都合で退職した場合、失業手当をもらうまでに「7日間の待期期間」+「原則2ヶ月間の給付制限」があり、実際に手当が振り込まれるまで約3ヶ月もかかりました。
これが、2025年4月1日以降に離職した人から、給付制限期間が原則「1ヶ月」に短縮されました!
ただし、注意点が3つあります。
- リスキリング(学び直し)に取り組んだ人は給付制限がゼロに!
- 離職前の1年以内に、国が指定する教育訓練(教育訓練給付の対象講座など)を受けていた場合、この1ヶ月の給付制限が適用されなくなり、7日間の待期期間後すぐに手当を受け取れます。
- 過去5年で2回以上、自己都合退職している人は「3ヶ月」のまま!
- 短期間に自己都合退職を繰り返している場合、ペナルティとして給付制限は3ヶ月のまま据え置かれます。
- このシミュレーションは上記1,2に当てはまらない「一般的な自己都合退職」のケースで進めます。
この変更により、退職後の資金計画が立てやすくなりました。それでは、具体的な金額を見ていきましょう。
あなたの失業手当は「いつから」「日額いくら」もらえる?徹底計算 🧐
まずは、あなたの生活を支える基本となる失業手当の金額を算出します。
Step 1: 賃金日額を計算する
失業手当の基準額は「退職前6ヶ月間の給与合計 ÷ 180日」で計算します。
- 月収25万円 × 6ヶ月 = 150万円
- 150万円 ÷ 180日 = 8,333円(賃金日額)
Step 2: 基本手当日額(1日にもらえる金額)を計算する
賃金日額に給付率(約50%~80%)をかけて、1日あたりの支給額を算出します。あなたの賃金日額(8,333円)の場合、以下のようになります。
- 基本手当日額: 約6,243円
これが、あなたが1日あたりに受け取れる金額です。
Step 3: 給付日数を確定する
自己都合退職の場合、給付日数は雇用保険の加入期間によって決まります。
- 雇用保険加入期間: 5年(10年未満)
- 給付日数: 90日間
※会社都合退職と比べて給付日数が短くなる点に注意が必要です。
【結論】あなたの受給スケジュールと総額
- 手続き後の7日間: 待期期間(受給対象外)
- 待期期間後の1ヶ月間: 給付制限期間(受給対象外)
- 受給開始: 退職後、ハローワークで手続きをしてから約1ヶ月と7日後からスタート。
- もらえる総額: 約6,243円 × 90日 = 最大561,870円
早く再就職すれば最大26万円!「再就職手当」というお祝い金 💰
「90日しかもらえないなら、早く決めないと…」と焦るかもしれません。しかし、その焦りがプラスになる制度があります。それが「再就職手当」です。
再就職手当をもらうための主な条件
- 失業手当の支給残日数が、所定給付日数(90日)の3分の1以上あること。
- 1年を超えて安定して勤務することが確実な職業に就いたこと。
- 待期期間と給付制限期間(1ヶ月)が終わった後の就職であること。
いくらもらえる?あなたのケースで計算
計算式: 支給残日数 × 基本手当日額(6,243円) × 給付率
ケース1:支給日数が3分の2以上残っている場合(給付率70%)
例えば、給付制限明けすぐに再就職が決まり、失業手当を1日ももらわなかった場合。
- 支給残日数: 90日
- 90日 × 6,243円 × 70% = 393,309円
なんと、約39万円の一時金がもらえます!
ケース2:支給日数が3分の1以上残っている場合(給付率60%)
例えば、90日のうち、30日分をもらってから再就職が決まった場合。
- 支給残日数: 90日 – 30日 = 60日
- 60日 × 6,243円 × 60% = 224,748円
この場合でも約22万円がもらえます。
転職活動がうまくいき、給付制限明けにすぐ内定が出れば、大きなボーナスになります。これを目標に活動するのも良い戦略です。
【最大の注意点】無職期間中の社会保険と税金のリアルな金額 😱
退職後の支出で最も重くのしかかるのが、社会保険料と税金です。特に自己都合退職の場合、会社都合退職のような保険料の軽減措置はありません。
1. 国民健康保険料:月額 約25,000円
前年の所得(年収300万円)を基準に計算されます。会社都合退職のような所得を3割とみなす軽減措置はないため、保険料は高額になります。
- お住まいの自治体によりますが、年収300万円の場合、保険料は月額25,000円前後になることが多いです。(※必ずお住まいの役所で正確な金額を確認してください)
2. 国民年金保険料:月額 16,980円(令和7年度)
所得にかかわらず一律の金額です。失業による支払いが困難な場合は「免除・納付猶予制度」を申請できます。役所の窓口で必ず相談しましょう。
3. 住民税:月額 約12,000円
前年の所得に対して課税されるため、無職になっても支払義務があります。年収300万円の場合、年間の住民税は約14万円~15万円程度。これを12ヶ月で割ると、月々12,000円程度の負担感になります。
【生活費シミュレーション】退職後のリアルな月間収支はこうなる!
自己都合退職の収支シミュレーションは、時期によって2つのフェーズに分かれます。これが非常に重要です。
フェーズ1:収入ゼロの期間(退職後〜約1ヶ月半)
待期期間(7日)と給付制限期間(1ヶ月)は、失業手当の収入が一切ありません。しかし、支出は待ってくれません。
収入の部: 0円
支出の部(固定費): 約53,980円
- 国民健康保険料: 約25,000円
- 国民年金保険料: 16,980円
- 住民税: 約12,000円
この期間は、貯金を切り崩して生活することになります。上記の固定費に加えて、家賃や生活費を支払う必要があるため、最低でも30万円程度の貯金がないと、かなり厳しい状況に陥ります。
フェーズ2:失業手当の受給開始後の期間
給付制限が明けて、ようやく失業手当が振り込まれ始めます。
収入の部: 約187,290円
- 失業手当: 6,243円 × 30日 = 187,290円
支出の部(固定費): 約53,980円
- (上記と同じ)
収支結果
収入 187,290円 – 支出 53,980円 = 133,310円
この約13万円から、家賃、水道光熱費、通信費、食費などを支払っていくことになります。最初の「収入ゼロ期間」を乗り越えられるかどうかが、自己都合退職における資金計画の最大のポイントです。
まとめ:退職を決める前に「お金の計画」を!
自己都合退職は、あなたのキャリアにとって前向きな選択です。しかし、その一歩を安心して踏み出すためには、周到な資金計画が不可欠です。
【今日のポイント】
- ✅ 失業手当の給付制限は原則「1ヶ月」に短縮された!(ただし例外あり)
- ✅ 最初の約1ヶ月半は収入がゼロになる。この期間の生活費を貯金でカバーできるかが最重要。
- ✅ 国民健康保険料に軽減措置はない!会社都合退職より負担は大きいと心得る。
- ✅ 年金の「免除・猶予制度」は必ず相談する!
- ✅ 早期の再就職は「再就職手当」という大きなメリットがある!
この記事のシミュレーションを元に、ご自身の貯金額と生活費を照らし合わせ、「いつまでに再就職するか」という目標を具体的に立ててみてください。計画的な準備が、あなたの素晴らしいネクストキャリアへの道を切り拓きます。







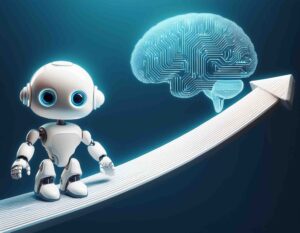


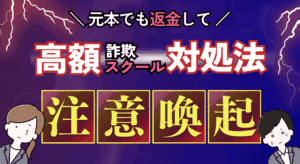
コメント