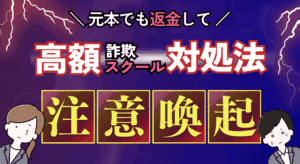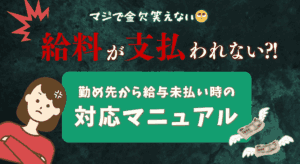同僚の逮捕が突きつける社会の闇:未成年淫行、法律の壁、そして裏切られた信頼の代償
ニュースの衝撃と心の底からの「どん引き」
スマートフォンに届いたニュース速報を見て凍り付きました。職場にいるはずの同僚が、未成年淫行の容疑で逮捕されたというのです。正直、「どん引き」という言葉だけでは表現しきれないほどの、深い嫌悪感と衝撃がすごすぎました。
職場では本当にいい同僚だったので、信じていた気持ちが一瞬にして崩れ去る感覚でした。
報道によれば、警察から青少年健全育成条例違反の容疑で逮捕されたとのことです。
容疑は、市内のホテルで18歳未満の女性とわいせつな行為をしたというものです。同僚は容疑を認めていると伝えられています。勤務態度は真面目でで、このような卑劣な行為に及んでいたという事実に胸が締め付けられる思いです。
「同意があれば問題ない」は間違い?未成年者保護の法的原則
このニュースを聞いて、多くの人が抱くであろう疑問が「相手が同意していたら問題ないのでは?」というものです。しかし、未成年者との性的な行為においては、たとえ本人が「同意」していると口にしたとしても、それが法的な意味での真の「同意」とは見なされない場合がほとんどです。
これは、未成年者が判断能力や社会経験が未熟であるため、大人の影響を受けやすいという現実に基づいています。
弁護士の見解によると、14歳から17歳の子どもとの性行為について「同意があれば合法なのか」という問いに対し、「原則的にアウト」「世の中で言われているような『同意があればOK』というような話は嘘だ」と強く否定しています。
これは、法律が未成年者を特別な保護の対象としているためです。
たとえ当事者同士に恋愛感情があったとしても、その関係性によっては警察が「未成年者保護」の観点から積極的に捜査を行い、摘発に乗り出すことがあります。今回のケースも、被害女性からの相談がきっかけで事件が発覚しており、その苦しみが想像に難くありません。
特に、大人と未成年者の間には、強い力関係が存在します。
弁護士は、たとえ強制的な行為がなかったとしても、お酒を飲ませたり、真摯な交際過程がない中で行われた性的関係は、「アウト」と見なされる可能性が非常に高い と指摘しています。
また、一般的に「性的意味を意味する行為でも相手の同意があればセクハラとはならない」という誤解があるかもしれませんが、周囲に不快感を与える場合はハラスメントになる可能性があります。性的接触を伴う行為は、社会通念上「普通やらないだろ」と判断されるような行為は問題視されます。容疑者が逮捕された容疑は「青少年健全育成条例違反」であり、この条例は未成年者の健全な育成を目的として、特定の行為を禁止しているものです。
犯罪がもたらす地獄:刑事罰と教員としての終焉
このような行為に及んだ加害者には、どのような厳しい代償が待っているのでしょうか。まず、報道にある通り、県青少年健全育成条例違反の容疑で逮捕され、刑事事件として立件されます。
これは、警察の捜査を受け、検察官の判断によっては起訴され、裁判で有罪となれば、懲役刑や罰金刑などの刑事罰が科されることを意味します。例えば、出資法違反の事例では「5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(併科あり)」、あるいは「10年以下の拘禁刑または3,000万円以下の罰金(併科あり)」 といった重い刑罰が定められています。
さらに、教員という専門性や公共性が高く求められる立場においては、社会的な非難は避けられません。このような事件を起こした教員は、まず間違いなく懲戒免職処分となります。過去にも、静岡県の県立高校の男性教師が18歳未満の少女にわいせつな行為をして免職処分を受けた事例が報じられています。
懲戒免職は、単に職を失うだけでなく、社会人としてのキャリアが永久に断たれることを意味します。一般企業においても、従業員や役員がこのような重大な不正行為、あるいは社会的な信頼を損なう行為を行った場合、会社は厳格な処分を下します。
役員や従業員による不正行為は「会社の社会的信用失墜」といった「大きな打撃」になりかねず、会社は損害賠償請求が可能である とされています。また、大手不動産会社が詐欺に騙され約55億円の損害を出した事件では、取締役の任務懈怠責任が問われ、株主から損害賠償を求められるケースも存在します。
人生を破壊する経済的代償:失業、再就職、そして自己破産のリスク
懲戒免職となれば、収入は途絶えます。失業手当(雇用保険の基本手当)を受給できる可能性はありますが、自己の責任に帰すべき重大な理由による解雇(いわゆる重責解雇)の場合、原則3ヶ月間の給付制限期間が加わります。会社都合退職の特定受給資格者であれば給付制限がないのとは対照的です。中にはは重責解雇に該当すると考えられる事があるため、すぐに手当が支給されるわけではありません。
今回の事件のように、犯罪行為で職を失った場合、社会的信用は失墜し、再就職の道はさらに閉ざされるでしょう。生活困窮に陥るリスクが高まることは容易に想像できます。
企業に与えるダメージ:信頼失墜と連鎖する波紋
この事件は、単なる一社員の不祥事では終わりません。容疑者が保育園や学校教諭といった子どもに関わる仕事をしている場合は勤務先への信頼が大きく揺らぎます。企業においても、従業員や役員による企業活動とは関係ない私生活上の犯罪行為であっても、幹部や役員によるものであればマスコミも注目し、勤務先として企業名が報道されることがあります。これにより、企業の社会的信用は大きく失墜し、売上減少や加盟店への営業補償といった大きな打撃を受けかねません。
また、このような不祥事が起きると、組織は迅速な対応を迫られます。事実関係の把握、客観的な証拠の収集、情報のコントロール、そして再発防止策の策定と公表が求められます。内部通報制度の整備も重要であり、公益通報者保護法によって通報者の保護が図られています。
私たちにできること:知識と警戒心で身を守る
このような中で、私たち一人ひとりが、このような悲劇を繰り返さないために未成年者を守っていく意識を持つ事が大切です。
そして、社会全体での監視の目を強化し、不審な行動や言動を見過ごさないこと です。
困った時は、警察の相談専用電話(#9110) や労働基準監督署、または弁護士 などの専門機関に相談することが重要です。
現代社会には、未成年者淫行のような倫理を逸脱した行為、そして巧妙な詐欺や経済的困難といった多様な「闇」が潜んでいます。同僚の事件は、私たちにとって身近なところに潜む危険と、それに対する無関心がもたらす悲劇を改めて突きつけました。
被害に遭われた女性が、この経験を乗り越え、心穏やかな生活を送れるよう、私たち社会全体で、精神的・社会的な継続的なサポートを提供していく必要があります。
加害者への憤りを感じると同時に、私たち一人ひとりが社会の一員として、このような悲劇を未然に防ぎ、健全な社会を築くために何ができるのかを真剣に考える機会である と捉えるべきです。