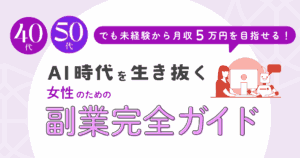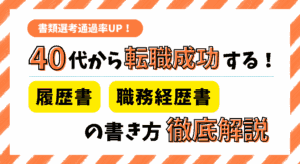職場の人間関係が原因で不調や体調不良が出て会社を休んでしまい、仕事でもやる気が出ずモチベーションも上がらないときにはどうすればいいのでしょうか?退職代行サービスや労働基準監督署に相談すべきか、他の方法があるのか考えていきましょう。
入社1ヶ月目はちょっと苦手だなというくらいだったのに、今ガチで無理だと思う上司や同僚の言動
職場での厳しい言葉や態度をとる人がいますが、大抵の場合本人に注意や改善を促す前に周囲が辞めていったり離れていき問題行動をとる社員の改善に至らないことがあります。具体的にどのような場合に「パワハラ(パワーハラスメント)」に該当するかについて理解することは非常に重要です。パワハラは、仕事の指導やアドバイスの範囲を超えて、個人の尊厳や心身に対して不適切な圧力をかける行為です。以下に具体的なパワハラに該当する言葉や態度の例を挙げます。
パワハラに該当する可能性がある言葉や態度の例
1. 人格否定や侮辱的な発言
- 「お前は何をやってもダメだ」
- 「そんなこともできないなんて、どうしようもない」
- 業務の指導の域を超えた人格や尊厳の否定や、人前で恥をかかせるような発言や、名指しで叱責する行為。
2. 過剰な叱責や怒鳴る行為
- 繰り返し大声で叱りつける、理不尽に怒鳴る行為。
- 一度のミスに対して執拗に非難を繰り返し、必要以上に追い詰める。
3. 不当な業務の押し付けや無理な仕事量の指示
- 1人で2人分の作業を強要したり、本来の役割や能力を超えた業務を強制的に押し付ける。
- 短期間で達成不可能な仕事量を課し、意図的に失敗させようとする行為。
4. 無視や孤立させる行為
- 話しかけても無視をする、仕事を教えない、仕事に関する情報を意図的に共有しない。
- 他の同僚と意図的に距離を取らせ、孤立させるような態度。
5. プライベートへの干渉や不適切な要求
- プライベートな時間に過度に干渉したり、仕事以外の不適切な要求をする。
- 家庭やプライベートな状況を批判するような発言。
6. 身体的な暴力行為や威圧や脅し
- 机を叩く、物を投げつける、叩くなどの身体的暴力行為。
- 実際に行動には移していないものの、危害を加える、仕事を与えないなど加害や妨害をほのめかす威圧的な発言。
7. 差別的な発言や不公平な扱い
- 性別、年齢、出身、容姿などに基づいて侮辱する発言。
- 特定の人物に対して理由もなく不当に扱う(昇進や評価の機会を意図的に奪うなど)。
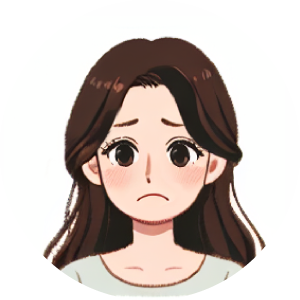
私も職場で苦手な人がいて、上長に相談して行動の改善を促したことがあります。とはいえすぐの改善には至らず仕事のパフォーマンスが低下して最終的には離職することになりました。
パワハラを受けたと感じたときの対処法


- 証拠を記録する
メールやメッセージ、会話の記録(できる限りメモを取るなど)を残しておくことが大切です。日時や状況を具体的に記録することで、後々の対応に役立ちます。 - 信頼できる同僚や上司に相談する
同僚や上司に相談し、第三者の視点からの意見を聞いてみましょう。特に信頼できる上司や人事部門に相談することで、問題が早期に解決する場合もあります。 - 会社の相談窓口を利用する
多くの会社にはパワハラを相談できる窓口があります。プライバシーを守りながら対応してくれることが期待されますので、勇気を持って相談してみましょう。 - 外部の機関に相談する
もし社内で解決が難しい場合、労働基準監督署や弁護士に相談することも考慮に入れるべきです。労働者の権利を守るためのサポートが得られます。
職場の人間関係が原因で病んだら
職場の人間関係が悪化すると、ストレスがたまり、身体や心に悪影響を及ぼすことがあります。仕事に行くのが苦痛になり、体調が崩れてしまうこともあります。このような状況に陥った場合、まずは自分の状態を正確に把握しましょう。具体的にどのような症状が出ているのか、どのくらいの期間続いているのかを把握することで、適切な対策を取ることができます。
退職代行サービスの利用を考える
もし職場の人間関係が改善しない場合や、自分の状態が回復しない場合は、退職代行サービスの利用を検討してみることも一つの方法です。退職代行サービスとは、本来ならば自分自身が行うべき退職手続きを代行してくれるサービスのことです。退職代行サービスを利用することで、自分の身を守りながら退職することができます。
労働局や労災の相談を受ける
職場の人間関係が原因で病んでしまった場合、労働局や労災の相談を受けることも考えてみましょう。労働局は労働問題に関する相談や労働条件の改善をサポートしてくれる機関です。また、労災とは職場での労働によって発症した疾病やケガを指します。労災に該当する場合、労働災害補償を受けることができます。職場の人間関係が原因で病んだ場合には、労働局や労災の制度を利用して自分の権利を守ることも重要です。
現職でメンタルを病んだ時は失業保険をもらいながら休職してメンタルを回復してから復職したらよいのか、すぐに転職すべきか
職場で心身ともに疲弊してしまい、次のステップを考えるときに「休職してメンタルを回復するべきか、それともすぐに転職すべきか」という悩みは大きいですね。どちらの選択肢にも利点とリスクがあるので、自分の状況や気持ちを踏まえて慎重に判断することが重要です。
以下に、失業保険をもらいながら休職するケースと、すぐに転職するケースについて、それぞれのメリットや注意点を説明します。
1. 失業保険をもらいながら休職し、メンタルを回復させてから復職する場合
メリット
- 心身の回復に集中できる
休職することで、仕事からのプレッシャーを一旦取り除き、メンタルや体調の回復に専念することができます。ストレスの原因から距離を置くことで、回復が早くなることもあります。 - 職場復帰の可能性が残る
休職をしている間は、法律上、職場との雇用関係は続いています。そのため、休職後に体調が改善すれば、元の職場に戻ることができます。慣れた環境に戻ることで、無理なく再スタートできることもメリットです。 - 傷病手当金が受け取れる
休職期間中に一定の条件を満たしていれば、健康保険から「傷病手当金」を受け取ることができます。給与の約3分の2が支給され、最長で1年6ヶ月間支給されます。これにより、経済的な負担が軽減されます。
注意点
- 職場の状況が変わらない可能性
休職後に復職しても、根本的な職場の問題や人間関係が改善されていなければ、再びストレスを感じる可能性があります。このため、休職中に復職後の環境改善を会社に相談することが必要かもしれません。 - 長期的な休職が難しい場合もある
会社によっては、長期的な休職に対して理解がない場合があります。また、休職期間が長くなると、復職後に業務への適応が難しくなる場合も考えられます。
2. すぐに転職する場合
メリット
- 新しい環境でリスタートできる
ストレスの原因となっている環境や人間関係から完全に離れ、新しい職場で気持ちをリセットできます。これにより、心身の負担が大幅に軽減されることが期待されます。 - キャリアの再スタートが早い
休職期間を取らずに転職することで、早い段階で新しいキャリアをスタートさせられます。特に、今の職場で長期的な成長が見込めない場合、転職は前向きな選択肢です。
注意点
- 転職先でも同じ問題が起こる可能性
転職した先でも、同じようなストレスや問題が発生するリスクはあります。特に、メンタルの回復が十分でない場合、新しい職場でうまく適応できないこともあります。休息を取ることが最優先の場合、焦って転職するのは避けた方が良いでしょう。 - 失業保険がすぐには受け取れない場合がある
自己都合で退職した場合、失業保険を受け取れるのは退職後3ヶ月程度の待機期間があります。その間の収入がなくなるリスクがあるので、生活資金の計画を立てる必要があります。
3. どちらを選ぶべきか?
- メンタルや体調が限界に近い場合
まずは休職して心身の回復を優先するのが良い選択です。自分の健康が最も大事ですので、無理をして転職活動を進めるとさらに状態が悪化することがあります。休職中に将来のキャリアについて考えたり、リフレッシュしながら体力や気力を取り戻すのが有効です。 - 今すぐ環境を変えたい場合
職場での人間関係や仕事の内容が根本的に合わないと感じている場合、転職も前向きな選択肢です。ただし、転職活動を進める中で、自分のメンタルや体調と相談しながら、無理なく進めることが大切です。
おすすめ転職サイト
最終的な判断のためのヒント
- まずは医師や専門家に相談する
精神的に辛いと感じているならば、医師やカウンセラーに相談することをお勧めします。適切なアドバイスを受け、休職が必要かどうかを判断してもらうと、より安心して決断できるでしょう。 - 家族や友人、信頼できる同僚に相談する
周囲の人々の意見も参考にしながら、自分にとって最良の選択肢を考えてみてください。
まとめ
職場の人間関係が原因で病んでしまった場合、自分の状態を正確に把握し、適切な対策を取ることが重要です。退職代行サービスの利用や労働局や労災の相談を受けることで、自分の身を守りながら問題解決に向けて進めるでしょう。ただし、これらの対策は最終手段であり、まずは職場の人間関係改善や自己ケアに取り組むことが大切です。自分を大切にし、健康な状態で働くことができる職場環境を求めることが重要です。