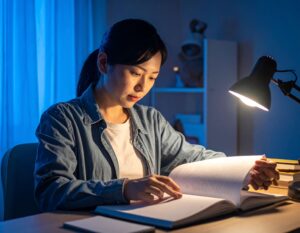社労士試験に落ちた母と息子の実話 ― Mrs. GREEN APPLEの音楽が、絶望の淵からもう一度立ち上がる勇気をくれた
こんにちは。今日は、キラキラした成功体験ではありません。むしろ、その正反対。うまくいかなかったこと、心が折れそうになったこと、そんな個人的な話を、少しだけ書かせてください。
今年の夏も、厳しい暑さでした。そして先日、私にとって、その暑さ以上に厳しい結果が突きつけられました。
数年間、人生を懸けて挑戦してきた「社会保険労務士(社労士)」の資格試験。結果は、「不合格」でした。
パソコンの画面に表示された、たった三文字。それを見た瞬間、サーっと血の気が引いていくのが分かりました。「なんでこんなに頑張ってもダメなんだろう」「もう年齢的にも記憶力が衰えているのかな」「生活のために働きながらなんて、やっぱり無謀だったんだ…」
次から次へと押し寄せる自己否定の波に、なすすべもなく飲み込まれていく。その日は、布団から一歩も出ることができませんでした。
この記事は、そんな不合格という厳しい現実を突きつけられ、どん底まで落ち込んだ40代の母親と、同じく夢破れた大学生の息子が、あるアーティストの音楽に支えられ、もう一度だけ顔を上げてみようと思えるようになるまでの、正直な心の記録です。もし、あなたも今、同じように分厚い壁の前で立ち尽くしているのなら、この物語が、ほんの少しでも、心を温める灯りになればと願っています。
第1章: 「不合格」― 親子で見た、あまりにも厳しい現実
私が社労士を目指そうと決めたのは、数年前のこと。子どもが大学生になり、想像を絶する学費の工面に、ただただ愕然としたのがきっかけでした。日中のパートに加え、夜間の仕事を掛け持ちする毎日。心身はすり減っていくのに、家計は一向に楽にならない。このままではいけない、何か専門的なスキルを身につけて、この状況を打開しなければ。
そんな思いで選んだのが、社労士の道でした。働き方の多様化が進む現代で、人と組織の専門家である社労士の役割は、ますます重要になるはず。自分の経験も活かせるかもしれない。そう信じて、眠い目をこすり、家族との時間を削り、必死に分厚いテキストと向き合ってきました。
追い打ちをかけた、息子の不合格
さらに胸が痛むのは、私に影響される形で「面白そうだね」と、同じく社労士の道を志した大学生の息子も、一緒に落ちてしまったことです。彼は彼で、資格学校に通い、慣れない法律用語と格闘していました。合格したら、親子でハイタッチして、ささやかなお祝いをするのが夢でした。でも現実は、食卓で二人して「…残念だったね」と力なくうつむくことしかできなかったのです。
普段は明るく、冗談ばかり言っている息子が、試験の後はため息ばかりついている。その姿を見るたびに、胸が締め付けられました。「私が無理して社労士なんて目指さなければ、息子までこんな辛い思いをさせることはなかったんじゃないか…」。そんな、母親としての後悔まで、黒い染みのように心に広がっていきました。
第2章: なぜ、これほどまでに心が折れるのか?社労士試験の過酷な現実
このどうしようもない挫折感は、単に「努力が足りなかった」という一言で片付けられるものではありません。社労士試験は、客観的に見ても、日本で最も過酷な国家資格の一つなのです。
2-1. 絶望的なまでに低い「合格率」
まず知っておくべきは、その合格率の低さです。例年、社労士試験の合格率はわずか6~7%前後を推移しています。これは、100人が受験して、合格できるのはたった6人か7人しかいない、ということを意味します。90人以上が、私たちと同じように「不合格」の通知を受け取っているのです。この事実だけでも、「落ちたのは自分だけじゃない」と少しだけ客観的になれるかもしれません。
2-2. 1000時間の壁―社会人にはあまりに重い「勉強時間」
社労士試験の合格に必要な勉強時間は、一般的に800時間から1000時間と言われています。仮に1000時間とすると、1年間で合格を目指す場合、毎日コンスタントに約2.7時間の勉強が必要です。フルタイムで働き、家事や育児をこなしながら、この時間を捻出することがどれほど困難か。それは、挑戦した人にしか分からない、壮絶な戦いです。
睡眠時間を削り、友人との付き合いを断ち、趣味の時間を全て返上する。そうやって捻出した「命の時間」を投じたからこそ、報われなかった時の反動は、計り知れないほど大きいのです。
2-3. 一発勝負のプレッシャーと広すぎる試験範囲
年に一度、たった一日の試験で全てが決まる。この一発勝負のプレッシャーは、経験した者でなければ分からない重圧です。さらに、労働基準法、労働安全衛生法、雇用保険法、国民年金法、厚生年金保険法…と、その試験範囲は膨大。法改正も頻繁にあり、常に最新の知識をアップデートし続けなければなりません。この果てしない道のりが、挑戦者の心を少しずつ削っていくのです。
心が折れそうになるのは、あなたが弱いからではありません。それだけ過酷な挑戦に、真正面から向き合った証なのです。
第3.章: 絶望のイヤホンから流れた希望の歌 ― Mrs. GREEN APPLEが教えてくれたこと
布団の中で、ただただ天井を見つめるだけの日々。食欲もなく、テレビの音も耳に入らない。そんな無気力な私を、そして同じように部屋にこもりがちになった息子を、少しだけ現実世界に引き戻してくれたのが、イヤホンから流れてきた音楽でした。
Mrs. GREEN APPLE(ミセス)。今や国民的バンドとなった彼らの音楽は、いつの間にか、私たち親子の共通言語になっていました。
出会いは、息子のサッカーの試合で流れた「僕のこと」
私がミセスを初めて意識したのは、息子がまだ高校生だった頃のサッカーの試合でした。惜しくも敗戦し、ピッチに崩れる選手たち。そのバックで流れていたのが、ミセスの「僕のこと」でした。
“僕らは知っている 奇跡は死んでいる
努力も孤独も 報われないことがある
だけどね それでもね 今日まで歩いてきた
日々を人は呼ぶ それがね、軌跡だと”
全力を尽くしても、夢が叶わないことがある。でも、そこに至るまでの日々、その軌跡こそが美しいのだと歌う歌詞が、泥だらけの息子の背中と重なって、涙が止まりませんでした。努力が必ず報われるわけではないという厳しい現実を肯定しながら、それでも、そのプロセスそのものに価値があるのだと教えてくれる。この歌は、それ以来、私にとって特別なお守りのような一曲になりました。
挫折と再起を歌う「Soranji」、全てを包み込む「ケセラセラ」
不合格の直後、あまりにも辛くて聴いていたのが「Soranji」でした。映画の主題歌にもなったこの曲は、深い喪失感や悲しみを抱えながらも、それでも生きていく理由を探す、祈りのような歌です。自分の無力さに打ちひしがれている時、この歌はただ静かに、その痛みに寄り添ってくれました。
そして、少しだけ時間が経ち、息子がリビングで珍しくテレビを見ていました。流れていたのは、レコード大賞を受賞した「ケセラセラ」。
“今日も誰かが言う「まぁ、いっか」
無責任な言葉が今は僕を救う
「大丈夫。」
魔法の様だ”
「なるようになる」。頑張りすぎて、自分を追い詰めていた私と息子にとって、その言葉は、張り詰めていた肩の力をふっと抜いてくれる魔法のようでした。「完璧じゃなくてもいい」「うまくいかなくても、まぁ、いっか」。そう思えた瞬間、久しぶりに、心が少しだけ軽くなった気がしました。
バンド自身の物語に重なる「再出発」の姿
私たちがミセスを好きになった理由の一つに、バンド自身の物語があります。人気絶頂の中での活動休止、そしてドラムの女性メンバーを含む2人の脱退。ファンとしては本当にショックな出来事でした。でも、彼らは3人組として、全く新しい音楽性と表現を携えて、見事に復活を遂げました。
形が変わり、別れや挫折を経験しても、また新しい形で、さらに力強く進んでいける。その姿は、一度試験に落ちたくらいで全てを諦めようとしていた私に、「終わりじゃない、ここからまた始められるんだ」という、静かな勇気を与えてくれました。
第4.章: 「もう一度」を考えるための、親子で踏み出す具体的なステップ
ミセスの音楽に少しだけ心を解かしてもらった私たちは、自然と、これからどうするかを話すようになりました。感情的に「よし、頑張ろう!」と奮い立つのではなく、一つひとつ、できることから整理していく。そんな、私たちなりの再起へのステップです。
ステップ1: 意図的な「勉強断ち」と「自分を甘やかす」期間を設ける
まず、二人で決めたのは「1ヶ月間、社労士のことは一切考えない」ということでした。テキストや問題集は、全て段ボールに詰めて押し入れの奥へ。これは「逃げ」ではなく、次へのエネルギーを蓄えるための、意図的な「戦略的休息」です。その間は、これまで我慢してきたことを思い切りしました。少しだけ贅沢な外食をしたり、一日中映画を見たり。罪悪感なく自分を甘やかすことで、すり減った心と体を回復させることを最優先にしました。
ステップ2: 敗因を「分析」する(犯人探しではなく、次へのヒント探し)
休息期間が終わる頃、私たちは一度だけ、今回の試験を冷静に振り返る「作戦会議」を開きました。目的は「どっちが悪かったか」という犯人探しではなく、「次に何をすればいいか」というヒント探しです。
- 私(母):「やっぱり仕事との両立で、圧倒的に演習量が足りなかった。特に選択式での1点に泣くパターンが多いから、細かい知識の精度を上げる必要があるね」
- 息子:「僕は逆に、全体像を掴むのが苦手だったかも。科目ごとの繋がりを意識できてなくて、知識がバラバラだった。あと、法改正のキャッチアップが甘かった」
このように、お互いの弱点を客観的に分析し合うことで、感情的にならずに次への課題を明確にすることができました。
ステップ3: 「チーム戦」という発想を取り入れる
これまでは、同じ目標を持ちながらも、それぞれが孤独に戦っていました。でも、二人で挑むからこそできることがあるはず。私たちは、次の挑戦を「チーム戦」と位置づけることにしました。
- 役割分担:得意な科目を分担し、要点をまとめたノートを共有する。
- 教え合い:私が苦手な年金科目を息子に教えてもらい、息子が苦手な労働判例を私が解説する。人に教えることは、最も効果的なアウトプット学習になります。
- 進捗管理:週に一度、お互いの勉強の進捗を確認し、励まし合う時間を作る。
孤独な戦いから、励まし合えるチーム戦へ。この意識の変化が、もう一度挑戦しようという気持ちを、何よりも強く後押ししてくれました。
ステップ4: 小さな成功体験からリハビリを始める
いきなり1日3時間の勉強を再開するのは、ハードルが高すぎます。私たちは、まず「1日15分、テキストを読む」という、絶対に達成できる目標からリハビリを始めました。そして、それができたら、カレンダーに大きな花丸をつける。「今日もできたね」と声を掛け合う。この小さな成功体験の積み重ねが、失いかけていた自信を、少しずつ取り戻してくれています。
第5章: 親子で挑むということ ― 最高の味方であり、ライバルでもある君へ
(この章は、少しだけ、母親である私から息子への手紙のような気持ちで書かせてください)
息子へ。
あなたが「俺も社労士、受けてみようかな」と言ってくれた時、お母さんは、正直、嬉しさと不安が半分半分でした。同じ目標を持つ仲間ができたことは心強かったけど、もし落ちてしまったら、あなたを辛い気持ちにさせてしまうんじゃないかって。
結果として、その不安は現実になってしまいました。あなたの落ち込む姿を見るのは、自分が不合格だったこと以上に、胸が痛かったです。ごめんね、こんな道に引きずり込んでしまって。
でも、この数週間、一緒に悩み、励まし合い、そしてもう一度立ち上がろうと話しているうちに、お母さんは、この経験が決して無駄じゃなかったと、心から思えるようになりました。
親子である私たちは、時に甘えも出るし、気まずくなることもあるかもしれない。でも、誰よりもお互いの状況を理解し合える、最高の味方です。そして、お互いの頑張る姿に刺激を受ける、最高のライバルでもあります。
来年の試験、どちらかだけが合格、ということもあるかもしれない。それでも、お互いの結果を心から祝福し合える、そんな親子でいようね。あなたが挑戦する限り、お母さんは、母親として、そして同じ受験仲間として、全力であなたを応援します。一緒に、頑張ろうね。
まとめ:挫折の先に咲く花を信じて
ここまで、私の個人的で、少し湿っぽい話にお付き合いいただき、本当にありがとうございました。
社労士試験に限らず、何か大きな目標に向かって挑戦しているすべての方へ。そして、その挑戦に敗れ、今、苦しんでいる方へ。
「落ちた」という事実は、本当に辛く、これまでの努力の全てを否定されたような気持ちになると思います。でも、ミセスの歌が教えてくれたように、その経験は、その軌跡は、決して無駄ではありません。むしろ、その痛みが分かるからこそ、人の痛みに寄り添える、深みのある人間になれるのだと信じています。
不合格という挫折を経験した私たちが、もし来年、社労士として誰かの相談に乗ることができたなら、机上の知識だけを振りかざすのではなく、相談者の不安や焦りに、心から共感できるはずです。そう考えると、この失敗も、未来への大きな財産になるのかもしれません。
私も、息子と、そしてMrs. GREEN APPLEの音楽に支えられながら、もう一度だけ、自分の可能性を信じてみようと思います。
もし、あなたが同じように挫折から立ち上がろうとしているなら、ぜひ一緒に、一歩を踏み出しませんか?
心が折れそうになったら、またミセスを聴いて。「僕のこと」に励まされながら。ゆっくり、私たちのペースで。